トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・民泊 > 食品等の安全 > 普及啓発 > 食中毒に注意しましょう > 有毒植物やキノコによる食中毒に注意しましょう
更新日:2024年6月7日
ページID:83120
ここから本文です。
有毒植物やキノコによる食中毒に注意しましょう
有毒植物による食中毒の発生
毎年、特に春先から初夏にかけて、有毒植物を食用の植物と誤って喫食したことによる食中毒が多く発生しています。
東京都内では、令和2年に自宅の庭に生えていたスイセンをニラと思い喫食したことによる食中毒が発生しています。
他県では、イヌサフランをギョウジャニンニクと思い喫食したことにより発症した事例や、ジャガイモの芽に含まれる天然毒素(ソラニン)の取り残しを原因とする食中毒が発生しています。

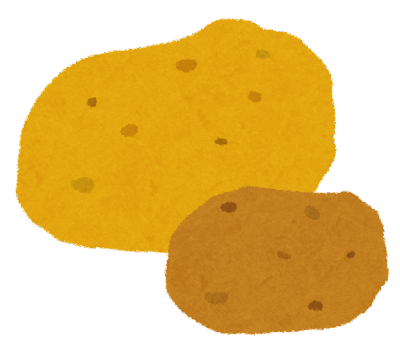
有毒植物による食中毒症状
食中毒事例が多いものについて紹介します。
1.スイセン
食後30分以内で、吐き気、おう吐、頭痛などの症状が出る。
2.イヌサフラン
食後2時間から半日の間に、おう吐、下痢、皮膚の知覚減退、呼吸困難などの症状がでる。重症化すると死亡することもある。
3.ジャガイモ
食後30分から半日の間に、おう吐、下痢、腹痛、めまい、動悸、意識障害、呼吸困難などの症状が出る。重症化すると死亡することもある。
有毒植物による食中毒を防ぐには
食用と確実に判断できない植物については、絶対に「採らない」、「食べない」、「売らない」、「人にあげない」ように注意しましょう。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
キノコによる食中毒の発生
令和5年9月、都内では12年ぶりにキノコによる食中毒が発生しました。
都外の公園で、インターネットの画像検索機能を用いて食用の可否を調べながらキノコを採取し、帰宅後に調理して喫食したところ、しばらくして錯乱、意識もうろう、おう吐、けいれん等の症状を呈し、緊急搬送されました。家庭に残っていたキノコの一部を検査したところ、テングタケであることが判明(毒成分であるイボテン酸が検出)しました。

毒キノコによる食中毒防止5カ条
1.食用と判断できないキノコは絶対に「採らない」「食べない」「人にあげない」。
2.キノコ採りでは、有毒キノコが混入しないように注意する。
3.「言い伝え」は信じない。
・柄が縦に裂けるものは食べられる・・・ウソ
・地味な色をしたキノコは食べられる・・・ウソ
・虫が食べているキノコは食べられる・・・ウソ
・ナスと一緒に料理すれば食べられる・・・ウソ
・干して乾燥すれば食べられる・・・ウソ
・塩漬にし、水洗いすると食べられる・・・ウソ
・カサの裏がスポンジ状(イグチ類)のキノコは食べられる・・・ウソ
4.図鑑の写真や絵にあてはめて、勝手に鑑定しない。
※インターネットの画像検索でも確実に鑑別することはできません。
5.食用キノコでも、生の状態で食べたり、一度に大量に食べると食中毒になるものがあるので注意する。
※体調に異変を感じたら、直ちに医療機関を受診してください。食べたキノコが残っている場合は、持参して治療の参考にしてもらってください。
関連リンク(厚生労働省ホームページ)
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品安全推進担当
電話番号:03-6400-0047
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。